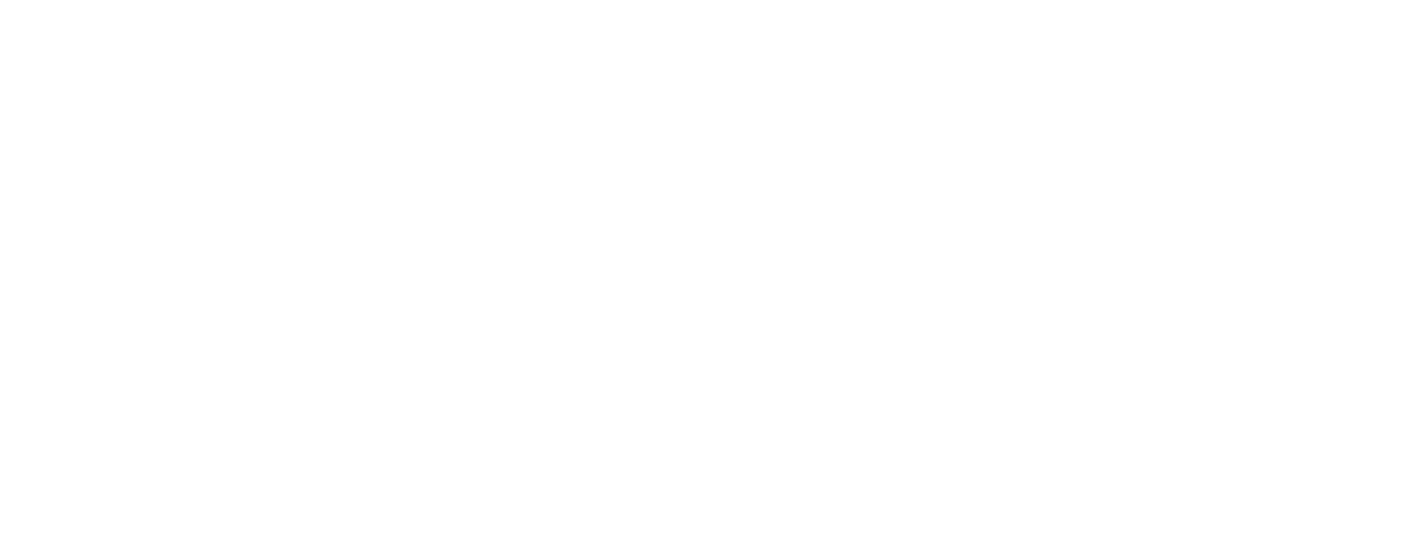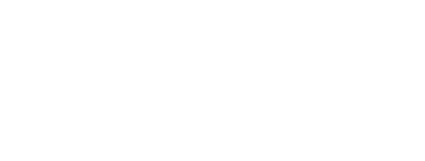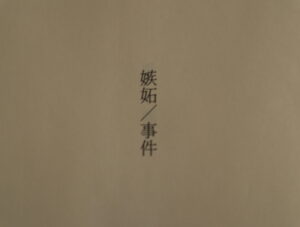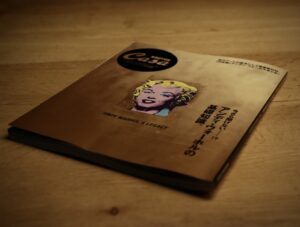5月 19日 正しさの概念、事実の多面性、描かれたオッペンハイマーの現代性について
どれほど強固な普遍性を持っていると思われる正義であっても、程度の違いこそあれ、それはその場に限ったコンセンサスや約束事に過ぎない。支配していたものは、宗教かもしれないし、時代背景かもしれないし、偏屈な指導者が指さす方向性や単なるその場の空気なのかもしれない。あるいはアメリカの安全保障における国防省の意向かもしれない。いずれにせよ、起こったことに対する絶対的な正しさそれ自体は存在しない。正しさとは、結局のところ、それぞれ自分が考えて判断する領域なのだ。