7月 16日 コーヒーを飲みながらルイジ・ギッリの写真集をめくって想うこと
中目黒epulorにはいくつかの美術書や写真をおいていますが、恵比寿・代官山epulor on the winding pathにも、レコードを聴きながら、コーヒーやワインともに楽しんでいただくのにぴったりな書物を置いていこうと思っています。

恵比寿の少し薄暗いバーで一人ウィスキーを飲んでいると、ある時にレコードが変わり、ニーナ・シモンの曲が流れ始めました。それまで何か考え事をしていたはずだったのですが、まるで自分の意識が支配されたかのように、僕は彼女の歌声をしばらくの間じっくりと聴き入ってしまいました。
どれほど強固な普遍性を持っていると思われる正義であっても、程度の違いこそあれ、それはその場に限ったコンセンサスや約束事に過ぎない。支配していたものは、宗教かもしれないし、時代背景かもしれないし、偏屈な指導者が指さす方向性や単なるその場の空気なのかもしれない。あるいはアメリカの安全保障における国防省の意向かもしれない。いずれにせよ、起こったことに対する絶対的な正しさそれ自体は存在しない。正しさとは、結局のところ、それぞれ自分が考えて判断する領域なのだ。
都心では交通の便が良いのと、歩いていても大抵の場所で高い建物に視界がおおわれるがゆえに、大まかな地形を把握することは容易ではない。しかしながら、「名は体を表す」というように、地名には地形や歴史が残されている。渋谷という「谷」から宮益坂という「坂」を上ると青山という「山」にたどり着く。丸ノ内線で新宿から銀座に向かう地下鉄線が四谷駅付近で地上にでるのは四谷がその名の通り「谷」だからだ。
エッセンシャルワーカーの人々が実際にどのような人となりで、どのようなライフスタイルで生きているかを、とかく意識しないしないですむということは、それ自体幸福なのか不幸なのかはわからない。作品中に、主人公が言っていた通り、一つの世界が全ての人に共有されているように見えていても、実は無数に分断された世界がそれぞれの接点を最小化するように共存しているにすぎない。幸福か不幸かはわからないにせよ、人々が望んで実現された現実なんだろうとも思う。
最近、繰り返し聴くアルバムがある。Brad Mehldauの「Your mother should know」、主にビートルズの曲をカバーしたライブアルバムだ。Brad Mehldauは最も偉大な現代ジャズピアニストの一人で、Pat Methenyとの共演などでも話題になり、日本にも何度か来て演奏している。そのうちの一つは「Live In Tokyo」というレコードにもなっている。
少し前に新聞を眺めているとセンター試験の現代文がたまたま目に入った。内容は、柏木博氏の『視覚の生命力―イメージの復権』の抜粋文(文章I)と呉谷充利氏の『ル・コルビュジエと近代絵画――二〇世紀モダニズムの道程』の抜粋文(文章II)を比較したものだったが、実に興味深かった。
ダブリナーズという小説がある。ユリシーズで有名なジェイムズジョイスによる短編集だ。1882年生まれのジョイスが、この短編集を1914年に正式に発表されるまでに10年近くを要したというのだから、初版を書き終えたのは20代前半ということになる。当時のアイルランド社会というか世相についての分析をストーリーテラーとして巧みに構成する技量を、その若さで持っていたという事でも、やはり歴史に残る卓越した作家というのがよくわかる。
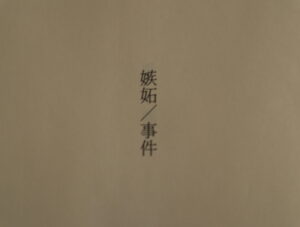
2022年9月から京都でアンディ・ウォーホルの展覧会「アンディ・ウォーホル・キョウト / ANDY WARHOL KYOTO」がスタートしたということで、いくつかの雑誌で彼の特集が組まれている。
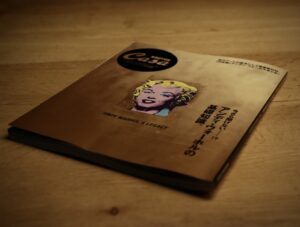
通知