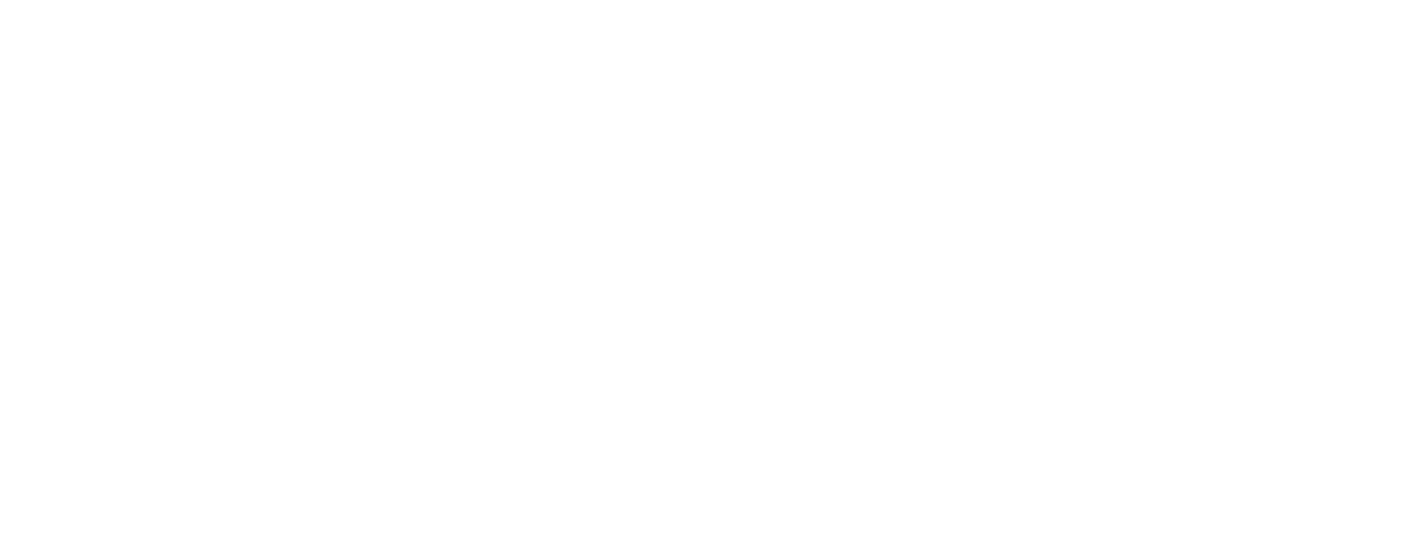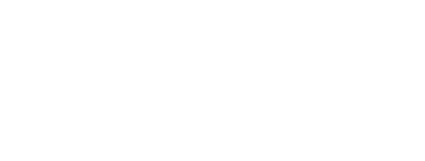4月 10日 分断された世界の接点、PERFECT DAYSがスポットライトをあてた部分とその影の部分について
エッセンシャルワーカーの人々が実際にどのような人となりで、どのようなライフスタイルで生きているかを、とかく意識しないしないですむということは、それ自体幸福なのか不幸なのかはわからない。作品中に、主人公が言っていた通り、一つの世界が全ての人に共有されているように見えていても、実は無数に分断された世界がそれぞれの接点を最小化するように共存しているにすぎない。幸福か不幸かはわからないにせよ、人々が望んで実現された現実なんだろうとも思う。
PERFECT DAYSの主人公の平山は、東京の公共トイレの清掃員で、真剣に仕事をこなしながら、質素で丁寧なルーティンの生活を送っている。60年代から70年代の古い音楽をカセットテープで聴きながら、文庫の小説を読み、小さな植物を育て、フィルムカメラで木漏れ日の風景写真を撮る。見方によっては文化的で豊かな生活だ。アニマルズ、オーティス・レディング 、パティ・スミス 、ルー・リード 、ヴァン・モリソン、ニーナ・シモンなど、彼が劇中で聴く趣味の良い音楽は、鑑賞する人に特別な印象を与えるはずだ。主人公の名前の”平山”は小津安二郎監督の「東京物語」の登場人物から、姪の名前の”にこ”はベルベッドアンダーグラウンドからとったものだろう。
一方で、彼がそういったライフスタイルを選択した以前には、まったく違った人生があったに違いないという示唆が作品に含まれている。高級車に乗る妹が、本当にトイレの清掃をしているのかと尋ねるシーンは、彼らの複雑な過去を想像させ、分断された世界の接点のきわどい部分が露になり、観る人の心をざわめかせる。その過去が具体的にどんなものなのか、最後のシーンの表情の訳は何なのかに対しては、最後まで答えが与えられない。明確に語られる物語というよりは、人々がそれぞれに感じるおぼろげなゆらぎの総体のようなものを、物語として提示したのだろう。
その試みは一定程度成功しているのは間違いない。ただ、物語にあてられているスポットライトの光源をたどると、それなりの偏りがかったいつもの場所にたどり着く。彼が着ていたユニフォームにある”The Tokyo Toilet”というのは実在するプロジェクト(https://tokyotoilet.jp/)で、発起人・資金提供者はユニクロの創業者一族の方だ。そのプロジェクトによって、東京の渋谷区のいくつかの公共トイレは、安藤忠雄、隈研吾、佐藤可士和、NIGO®など豪華メンバーでデザインされている。映画化に際しては、電通グループの方がかかわり、監督には「パリ、テキサス」、「ベルリン・天使の詩」、「ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ」などを手掛けたヴィム・ヴェンダー氏が起用された。
社会的・文化的エリートが、コンプライアンス時代のポリティカルライトネスに正しく芸術作品を提示し、見事に世間から評価され、主演俳優はカンヌ国際映画祭男優賞をも受賞された。もちろん、文句のつけようがない文化的業績だ。ただ、ほんの少し、分断された世界の接点の、スポットライトが当たらなかった(あるいは避けられた)部分に対して、反射的に思いをはせると、なんともいいがたい気持ちになる。もしかすると、それさえもこの作品の狙いなのかもしれないのだが。
トイレの汚れが酷くない事、同僚のタカシが適度にいい人である事、なぜか平山が女性からモテる事、彼が結局のところ本質的にエスタブリッシュ側の人間であることが示唆されている事、それらで覆い隠された本当の現実に目を凝らしてしまうのは、ある程度に強い意味を持つメッセージ性が存在するうえの必然であろうか。
ちょうど数日前、小澤征爾氏が死去した。村上春樹氏は寄稿した記事の中で、彼の音楽を以下のように評価している。
そこには過度なメッセージ性もないし、大げさな身振りもないし、芸術的耽溺もなく、感情的な強制もない。そこにあるのは、小澤征爾という個人の中に確立された純粋な音楽思念の、虚飾を排した誠実な発露でしかない。
村上氏がコメントを通じて何かに対するアンチテーゼを示しているのかは全く定かではないが、虚飾を排した純粋な芸術性も、時代に沿ったメッセージのもつ芸術性も、どちらの存在も認めるべきだと僕は思う。そもそも僕には、芸術というものが本来どうあるべきか、ということに関して意見できるほどの見識を持ち合わせていない。確からしく言えそうな事があるとするなら、メッセージがあろうがなかろうが、感情的な強制があろうがなかろうが、いい芸術作品はそれなりに長く多くの人の感情を揺さぶるものなのだ、ということではないだろうか。