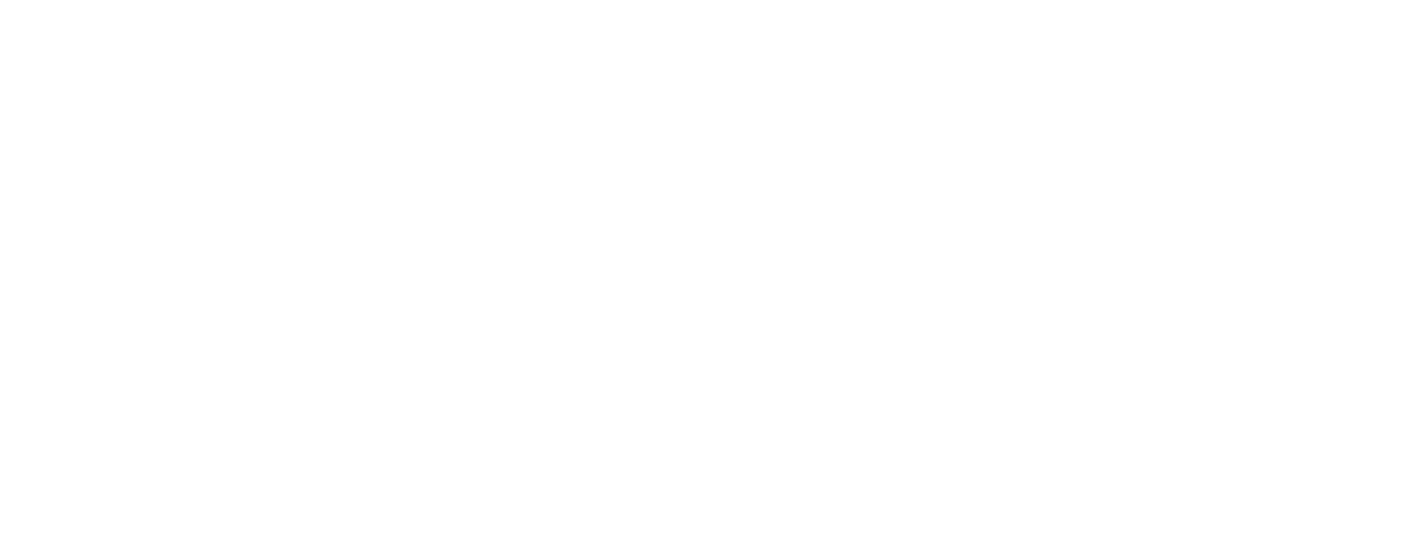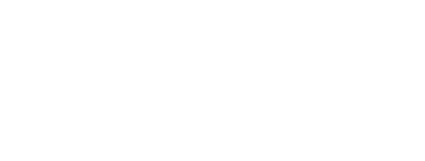5月 19日 正しさの概念、事実の多面性、描かれたオッペンハイマーの現代性について
どれほど強固な普遍性を持っていると思われる正義であっても、程度の違いこそあれ、それはその場に限ったコンセンサスや約束事に過ぎない。支配していたものは、宗教かもしれないし、時代背景かもしれないし、偏屈な指導者が指さす方向性や単なるその場の空気なのかもしれない。あるいはアメリカの安全保障における国防省の意向かもしれない。いずれにせよ、起こったことに対する絶対的な正しさそれ自体は存在しない。正しさとは、結局のところ、それぞれ自分が考えて判断する領域なのだ。
僕が学生だった90年代の後半に、テーマを設定して討論する授業に参加した事があった。その時のテーマは「広島・長崎に原爆は落とすべきだったか」というものだった。もちろん、「落とすべきではなかった」という論調が支配した。日本人であれば、その理由はいくらでもあげることができる。討論が終わりにさしかかった時に、社会学者の先生がおもむろにコメントした。彼は何度も色んな国で同じテーマで討論したが、日本を除く全ての国で、原爆投下はいたしかたなかった、という結論だったのだという。今よりもっと無知だった僕にとってはそれなりに衝撃的な話だった。
今なら、もう少し状況を理解する事ができる。戦勝国にとって日本は第二次世界大戦の「加害者」であり、降伏するはっきりとしたキッカケを与えなかったら、いずれ本土決戦に突入し、両国でより多くの戦死者が増えていたに違いない(それに、原爆の実戦使用は、アメリカにとって戦後の世界秩序において重要な位置付けだった)。それが彼らの基本的な論理構成なのだそうだ。
事実は一つでも、その形状は常に多面体だ。トルーマンにはトルーマンの、オッペンハイマーにはオッペンハイマーの、広島・長崎に住んでいた市民一人一人には、それぞれに、それぞれ別の側面がある。自分の見えている側面だけで事実を語っても理解には限界がある。物事をもう少し核心的に理解する上では、多面的視野が必要だ。
オッペンハイマーの直面した苦悩は、とても独特で重要な意味をもつ。原爆の父というのは、功績者をたたえるためであっても、彼にとっては複雑な気持ちだったのだろう。周りとの温度差は大きく、それは彼を孤独にし、ひどく悩ましたに違いない。ポンと肩を叩かれて、君は正しいことをしたんだよと言われても、ことの重大さを軽視できるほど単純な性格ではなかったのだろう。
戦後のアメリカの安全保障上の戦略的重要性が、対日独から共産国家に変わると、あらゆる評価は一変した。戦時中アメリカのプロパガンダにより大衆メディアでUncle Joe(ジョーおじさん)と親しまれていたスターリンは、最悪の独裁者として敵視されるようになった。ジョージ・オーウェルのディストピア小説が語るように当時の反共はほとんど恐怖による反射的な敵意だった。
1950年代まで激しく続いたマッカーシズム(赤狩り)では、多くの才能ある人々のキャリアが致命的に損なわれた。チャップリンは事実上、国外追放になったし、第二次世界大戦終結の功労者であった天才科学者オッペンハイマーでさえも例外ではなかった。最終的に彼の名誉は回復するが、映画においては、彼の功績として世界に残した重みと共に、穏やかな悲劇として幕を閉じている。時々の人間の評価する正しさがいかにうつろいやすくとも、今を生きる人々に残されたものはずっしりと重い。映画で強く訴えられている部分だ。
物語は1940年代〜1950年代を主な舞台としているが、作品は極めて現代的であると思う。冷戦終結以降から徐々に希薄化されていく核への恐怖に対する危機感や、今もなお直面している戦争と共に、アメリカをはじめとしたに西側諸国における多様性の評価が反映されている。オッペンハイマーの人生を描く上で、天才科学者としての評価、マンハッタン計画での功績、反共時代における対応が注目されがちだが、それだけでなく原爆開発の功罪や彼の持ち続けた苦悩に対して大きくスポットライトが当たっているのは特筆すべき点だと思う。少し前の時代の映画ならこのような形にはなっていなかったであろうし、アカデミー受賞での評価も難しかったかもしれない。
政治的な決断や行動に対する評価は、同時代を生きた人々には難しく、未来の歴史家のなすべき仕事だとされる。現代性を反映した今回の映画が、彼に対するある程度定まった評価になりつつあるのかは、正直に言って今一つ確信が持てない。それは僕が日本人だからだろうか。